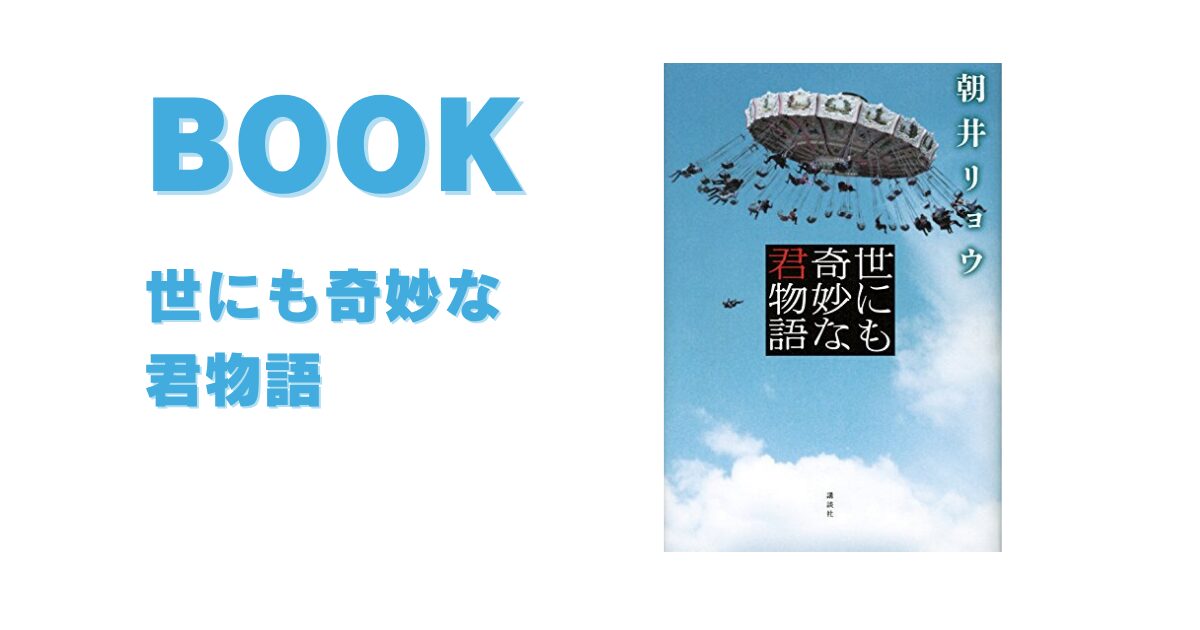朝井 リョウのエッセイ『そして誰もゆとらなくなった』を読んで、やはりこの人の物事の捉え方や発想が面白いなと感じた。きっとスルーしがちなことを自分の感覚に引っ掛けて、ネタにするセンスがある。そして本屋を歩いているときに『世にも奇妙な君物語』を見つけた。表紙は何度か見たことがある。せっかく朝井 リョウにハマっている時期だし、読んでみるかと手に取った。
『世にも奇妙な君物語』概要
朝井リョウの小説『世にも奇妙な君物語』は、現代社会に潜む違和感や矛盾を、ユーモアと皮肉を交えて描いた短編集である。収録された5つの物語はいずれも独立しているが、共通して「正しさ」「常識」「同調圧力」といったテーマを扱い、読者に自分の日常を照らし返すような感覚を与える。
物語の舞台は私たちが暮らす社会とほとんど変わらないが、そこには奇妙なルールや制度が導入されている。一見すると身近でありふれたシーンに、ほんのわずかな歪みが加えられていて、その歪みが登場人物たちに強烈な不安や葛藤をもたらし、やがて私たち自身が抱える息苦しさや理不尽さと重なっていく。
軽妙で読みやすく、同時に鋭い観察眼が貫かれている。会話や心情描写には笑いを誘う要素がありながら、その背後には「なぜ私たちはここまで正しさを求め合うのか」「常識とは誰のためのものか」といった根源的な問いが潜んでいる。作品を読み終えた後には、日常の価値観がぐらつくような余韻が残る。
『世にも奇妙な君物語』感想(ネタバレちょっとあり)
面白かった。私は特に1つ目の「シェアハウさない」と、2つ目の「リア充裁判」が好き。
「シェアハウさない」は、一見普通の男女4人が暮らすシェアハウスに、ライターの浩子が職業を隠して入り込む話。シェアハウスについての特集を担当することになった浩子は、シェアハウスの中に自然と入れる偶然のチャンスを活用しようと考えていた。しかし、物語の後半、ある事実が明らかとなる。
「普通」に見えて普通じゃなくて、もがく人たち。その人たちの苦しみや葛藤。「普通」になりたくて、似たような人たちを集めてお互いを見守っていた。それでも個人の「こだわり」はなかなか抜けないようで…。朝井 リョウの小説『正欲』で抱いた感情と読後感と似ていた。個人が抱える問題や社会問題を、読者が共感できるように書かれている印象。
「リア充裁判」は、20XX年に施行された「コミュニケーション能力促進法」に定められた通りに行われる裁判の法廷をメインで描いた話。この法律のもとでは、「SNSのアカウントがある」「大学生活で、先輩の車でバーベキューに行く」「キムチやチョコをいれるたこ焼きパーティーをしている」などしていないと、「ひとりよがりで、孤立している」と判断されてしまう。熱心に勉強をして、妹想いのお姉ちゃんだったとしても。
「シェアハウさない」「リア充裁判」を含め、ほかの3つの短編も、何かしら「社会に当たり前にはびこっている考え方」や社会問題に対して一石を投じるテーマ。そのような話に興味がある人は、ぜひ読んでみると良いと思う。