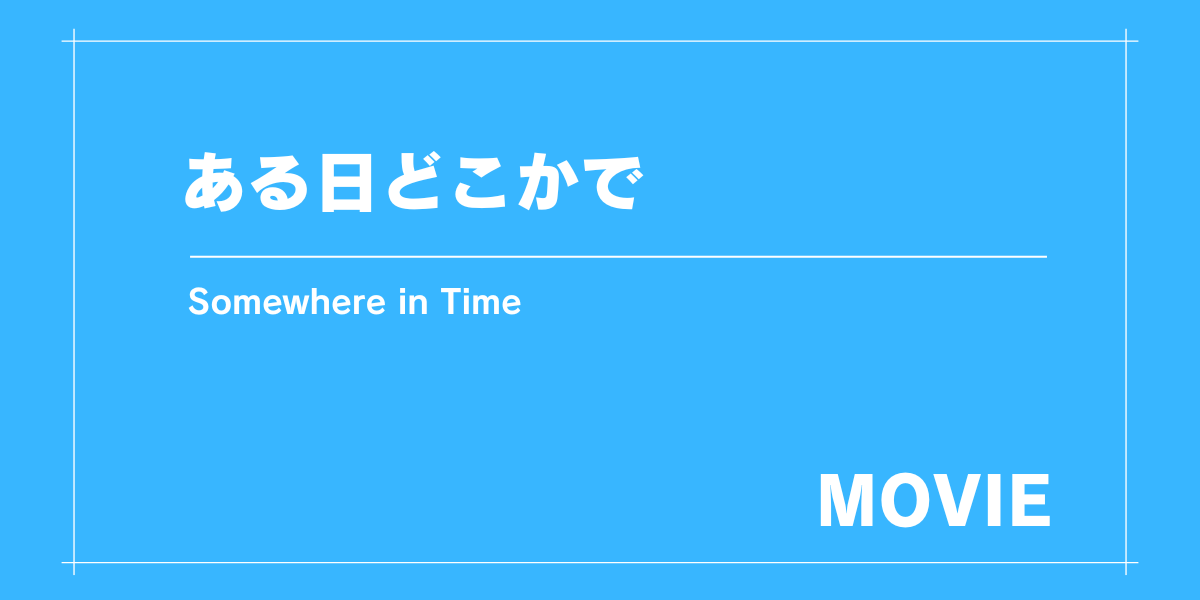『ある日どこかで』概要(ネタバレなし)
映画『ある日どこかで』(原題:Somewhere in Time、1980年)は、時を超えた愛を描くロマンティックなファンタジー映画。
若き劇作家リチャード・コリア(クリストファー・リーヴ)は、自作の初演の夜、見知らぬ老婦人から「帰ってきて…」という謎の言葉と共に懐中時計を手渡される。
8年後、スランプに陥ったリチャードは、気晴らしに訪れた「グランド・ホテル」で、1912年に滞在していた美しい舞台女優エリーズ・マッケナ(ジェーン・シーモア)の写真に強く惹かれる。彼女こそ、かつて懐中時計を渡した老婦人であることを確信したリチャードは、独学でタイムトラベル理論を考案し、自己催眠によって1912年へと旅をする。そしてついに、時間の壁を越え念願の彼女と出会う。
ラフマニノフ(パガニーニの主題による狂詩曲)が全編に流れ、美しい映像と音楽が切ない愛を際立たせる、名作として長く愛されている作品。
『ある日どこかで』感想
1980年製作の映画ということで「映像や音声は古いんだろうな。きっと途中で観るのやめちゃうだろうな」と期待半分でスタートした。しかし、今から40年以上も前の映画とは思えないほど、綺麗な映像と風景、衣装で、少しだけ夜更かしして観終えた。
主人公のふたり、クリストファー・リーヴとジェーン・シーモアが美しい。途中からはふたりを見るために映画を観ていた言っても過言ではないくらい。クリストファー・リーヴ演じるリチャードが、1980年から1912年へタイムトラベルをした後の、ホテルにいる人々の衣装がとても上品かつ可憐で、その雰囲気に飲まれていった。
クリストファー・リーヴが演じるリチャードが現代で会った、ホテルのスタッフである老人アーサーと、1912年でも会ったシーンが印象に残っている。1912年のアーサーは、まだボール遊びをしたいばかりの子どもで、よくお父さん(?)から怒られていた。ちょっと下膨れで頬が赤く、かわいかった。誰しも子ども時代があったんだなあと感じさせられた。
作中で使われた、ラフマニノフの音楽
作中では、セルゲイ・ラフマニノフの『パガニーニの主題による狂詩曲』が使われている。
セルゲイ・ラフマニノフ(1873年〜1943年)は、ロシア出身の作曲家・ピアニスト・指揮者。ピアノ協奏曲や交響曲を多く作曲し、特に「ピアノ協奏曲第2番」は名作として今でも世界中で広く演奏されている。ロシア革命後にアメリカに亡命。
私は趣味でピアノを続けていて、それなりに難しいと言われる曲も弾いてきた。人様に聴かせられるような技量ではないが、ベートーヴェンの「月光」「悲愴」それぞれ1〜3楽章や、リストの「ラ・カンパネラ」など。いつでも「好きな曲を弾けるようになりたい!」という一心で練習をしていた。
ある日、ラフマニノフの「10の前奏曲 Op.23: No.5」を聴いて衝撃を受け、弾きたいと思い挑戦したが、難しくてやめた。それ以来、ラフマニノフの音楽をいくつか聴いているうちに曲の美しさに魅了され、今では好きな作曲家のひとりになった。特にピアノとオーケストラのために書かれた「ピアノ協奏曲第2番」や、オーケストラのための「交響曲第2番」はラフマニノフの代表作。今でもさまざまな楽団によって演奏されている。
話が逸れてしまったが、『ある日どこかで』で使われる『パガニーニの主題による狂詩曲』は、パガニーニというバイオリニストによる「24の奇想曲」の第24番が主題となっており、ラフマニノフが24の変奏で構成した作品。ややこしいのでざっくりと説明するなら、バイオリニスト・バガニーニの曲を、ラフマニノフが編曲した曲。
ちなみにパガニーニは超絶技巧を駆使して、ほかの演奏家が真似できないレベルで演奏をしたため、「ヴァイオリンの鬼神」や「悪魔に魂を売った」と言われるようになったそう。彼の曲に立ち向かいたいピアニスト・作曲家によって、パガニーニの曲をピアノ用に編曲されたものがいくつもある。ラフマニノフの『パガニーニの主題による狂詩曲』は、そのうちのひとつ。
さいごに
クラシック音楽好きがゆえに、映画よりも音楽について長々と書いてしまったが、映画自体もとても良かった。とにかくすべてが美しい。そして最後、きっとあの世で再び出会ったであろう結末も良かったと思う。